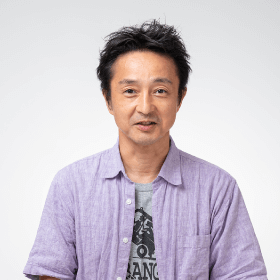【ユタカの部屋vol.47 松浦加奈氏】
焼物との出会い、そして「上の畑焼」へ
—— まずはお名前をお願いします。
松浦加奈(まつうら・かな)と申します。本名は松浦加奈子ですが、陶芸の仕事では「加奈」として活動しています。雅号のようなものですね。
—— この焼物との出会いについて教えてください。
もともと両親がこの「上の畑焼(かみのはたやき)」を生業としていて、幼い頃から自然と身の回りに焼き物がある生活でした。私自身、絵を描いたり書道をしたり、音楽を楽しんだりと、ものを作るのが好きだったんです。
でも、両親が仕事に苦労している姿を見て、「これは仕事にはできないな」と思って、別の道を考えていました。勉強も好きだったので、大学では法学や政治経済を学ぶことにしました。絵本作家や新聞記者になりたい、というささやかな夢もありました。
—— 大学は東京だったんですね。
はい、東京の日本大学に進学しました。そこで一人暮らしを始めて、学生課の掲示板で見つけたアルバイトが、焼物のギャラリーの仕事だったんです。浅草のギャラリーでした。「これ、私にできる!」と直感して応募しました。
そのバイトをきっかけに、焼物の作家さんと知り合って、陶芸教室の手伝いもするようになりました。都内の女性陶芸家さんのアシスタントも経験して、初めて「形を作るって面白い」と感じたんです。
—— それで、焼物の道へ?
そうですね。大学で社会や政治を学ぶのは楽しかったけど、「これを仕事にするのは違うかもしれない」「やっぱり焼物の方が向いているのかもしれない」と思うようになったんです。親に「焼物をやりたい」と伝えたら驚かれましたが、「まずは大学を卒業しなさい」と言われて、卒業後に改めて学び直すことにしました。
—— どちらで学ばれたんですか?
佐賀県にある「佐賀県立有田窯業大学校」です。有田焼の産地ですね。そこでは2年間、すごく濃密な時間を過ごしました。地元の職人さんたちの元で学ぶ機会もありましたし、みんな本当に焼物に真剣に向き合っていて、お金のためじゃなく、「好きだから作る」という姿勢に衝撃を受けました。
—— 焼物に向き合う心構えを学んだんですね。
まさにそれです。大学では技術だけでなく、「焼物を仕事にするとはどういうことか」という心の持ち方を学んだ気がします。今でも「お金じゃない」と思えるし、自分の手で作ったものを誰かが「使いやすい」「素敵」と言ってくれるだけで、それがご飯のようなものです。
—— それで山形に戻ってこられて?
はい。有田での学びを経て、まずは家の仕事を手伝おうと思って戻ってきました。うちの父は三重県の萬古焼(ばんこやき)で修行して独立した人なんです。萬古焼は陶器の一種で、私が学んだ有田焼は磁器。原料や焼成方法など、作り方がまったく違うんですよ。
—— 陶器と磁器の違いも大きいんですね。
大きな違いは、まず原料です。陶器は山の粘土をそのまま使いますが、磁器は石(例えば透石)を砕いて水と混ぜて粘土状に加工します。また、焼成方法も異なっていて、磁器は「還元焼成」といって、窯の中を酸素の少ない状態にして焼きます。陶器は逆に、酸素をどんどん送り込む「酸化焼成」で焼きます。
—— 「上の畑焼」は磁器になるんですね。
はい。私たちが作っている「上の畑焼」は、原料に石を使う磁器です。焼き上がりは白くて硬く、金属的な音がします。一方、陶器は柔らかい色味で、空気を多く含んでいるので音も鈍く、性質も用途もかなり違います。
—— 工程としてもやはり大変ですか?
磁器は特に、原料の石を砕くところから始まるので、工程がとても多いです。石を砕いて、水を混ぜて、鉄分などの不純物を取り除き、フィルタープレスという機械で水分を抜いて、粘土を作る。それからやっと成形、乾燥、削り、焼成と続きます。
—— 手間暇かかっているんですね。
はい。でも、その手間こそが面白いし、魅力でもあると思っています。
「上の畑焼」という土地で焼物を続ける理由
——有田で学びを深めた後、山形に戻ってこられたのはやはりご両親のもとで家業を手伝うという思いが強かったのでしょうか。
はい、そうですね。山形に戻ってきたのは、まず両親の仕事を手伝うという思いからです。焼物の世界って、誰かに弟子入りする人もいれば、大学で学んで独立する人もいる。私は後者だったので、修行というより、学問として陶芸を学んで、自分の中で向き合い方を整えて戻ってきたという感じですね。
——山形、特に「上の畑」という土地で焼物を続ける理由について、どんな思いをお持ちですか。
「上の畑焼」というのは、父が始めた窯の名前であり、この土地で焼物をすることそのものが、私たち家族にとっての営みそのものなんです。正直なところ、焼物をするには決して恵まれている場所とは言えません。山形は陶芸の産地ではないし、冬は厳しいし、インフラも整っているわけではない。でも、だからこそ、自分たちで考えて工夫して、作り上げていく面白さがあるんです。
——焼物の制作過程についても、非常に丁寧に取り組まれている印象があります。
はい。うちは原料からすべて自分たちでやっています。粘土も石から砕いて、水を加えて練って、フィルタープレスで不純物を抜いて…その上でろくろや型作りなどで成形していきます。磁器なので、焼成も還元焼成という方法で酸素を抜いて硬く焼き上げます。どの工程も、妥協しないでやることが、最終的な作品の「品」に現れると思うんです。
——「品」とおっしゃいましたが、作品に込める思いについてもう少しお聞かせいただけますか。
私は、「自分の作品が誰かの暮らしの中にすっと溶け込んで、役に立ってくれたらそれでいい」と思っています。毎日手に取る湯呑みやお皿。何気なく使っているけれど、ふとした瞬間に「これ、いいな」と思ってもらえる。そんな器を作りたい。そのためには、土にも火にもきちんと向き合わないといけない。焼物って、本当に手を抜くとすぐにバレるんですよ。だからこそ、丁寧に、正直に、作っていきたいと思っています。

——最後に、「上の畑焼」として、今後目指す姿や夢を教えてください。
「上の畑焼」という名前は、この土地と共にある焼物という意味でつけられました。だから、これからもこの土地で、風土に合った器を作り続けていきたいですね。あとは、もっと多くの人に焼物の魅力を伝えていけたら嬉しいです。器って、人と人とを繋ぐ存在でもあると思うので。何十年先も、変わらずここで窯の火を絶やさずにいられたら、それが一番の願いです。
 ウジイフォトスタイル
ウジイフォトスタイル